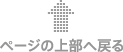【公 演】郷古 廉(ヴァイオリン)インタビュー(取材・文:青澤隆明)
2024.09.01

取材・文:青澤隆明
ヴァイオリニストの郷古廉が11月、杜のホールはしもとのステージに初めて登場する。
10代半ばから注目を集めてきた新鋭も30代に入り、NHK交響楽団の第1コンサートマスターとしての重責も担いつつ、音楽家としての新しい季節をしっかりと歩んでいる。
この秋は、2018年から共演を重ねるピアニスト、ホセ・ガヤルドとともに多彩なプログラムでデュオ・リサイタルを行う。ブエノス・アイレス出身で長くドイツ拠点とするガヤルドは「懐が大きく、いろいろなことを試せるし、自分の即興的な部分をすごく引き出してくれる」と郷古も讃える室内楽の名手である。
注目のプログラムは、チャイコフスキー、シューベルト、ラヴェル、フランクの名作。大陸を大きくわたり、時代的にも18世紀から20世紀前半まで200年におよぶ壮大な旅となる。
多彩な名曲の背景には、当代一流のヴァイオリンの名手たちの存在があった。シューベルトの《幻想曲》にはボへミアのスラヴィークが、チャイコフスキーにはラロの《スペイン交響曲》を通じてサラサーテの影響が、フランクの《ソナタ》にはベルギーのイザイ、ラヴェルの《ツィガーヌ》にはハンガリー出身のダラーニが深く関わっていた。
――ヴァイオリンの名作の多くが、当時の名演奏家に触発されて生まれました。郷古さんは古い演奏はよくお聴きになるほうですか。
僕が歴史的な名手たちを知ったのは、本当に遅かったと思う。両親は音楽家ではなかったし、特定の誰かに憧れた経験もないんですよ。いわゆる巨匠の演奏に触れはじめたのは、中学生になってからくらいでした。
――自分がしゃべれるようになってから、ネイティヴの発音を聞くみたいな感じだったのですね?
そうだったかもしれないですね。聴いたときにはもちろん、衝撃を受けました。こんな人たちがいたんだ、と。
映像も白黒でしたから、彼らの巧さに衝撃を受けたというよりは、こんなにむかしの人たちもここまで楽器を究めようとしていたんだって、ちょっと不思議な感覚に陥りましたね。
――それは、譜面をみれば聞こえてくるから、他人の発言は関係がないという感じなのですか?
べつにそこまでのことではなくて。聴いてすごく素敵だなと思うことも、もちろんたくさんあります。ただ、みんなそれぞれに良さがあるし、欠点もあるし、べつに完璧なものはないと思っていて。だから、こういう視点もあるんだ、というような感覚ですよね。
――なんと言うか、郷古さんはあまり相対的な人ではない感じがするんですよ。誰かと比べてどうというのではなくて、最初からヴァイオリンをもってここにいた、というような。
そう思っていただけているのだったら、うれしいな。
――作品と向き合うとき、たとえば今回の曲にはダラーニやイザイのエッセンスも出てくるでしょうけれど、郷古さんはおそらく、その人のふりをしようとはしないですよね?
しないです。ただ、「よりヴァイオリニストとして演奏する」というか、「楽器を演奏するということ」はより強く意識しますね。シューベルトの《幻想曲》でさえ、スラヴィークというきっとものすごく弾けた人がいて、そうでなければあのような弾くのも不可能みたいな曲は書かないでしょう。
――《幻想曲》ハ長調は、シューベルト晩年の大傑作で、極めつきの難曲でもありますね。
これ以上の曲があるのかな、というぐらいのクラスの曲だと思います。ピアニストにとっては地獄のように難しい曲で、ヴァイオリニストにとってもそう(笑)。あれだけの緊張感を演奏者に強いる曲もないと思う。
――名演奏家が作曲家の創作力を刺激して、技巧や語彙が拡がるのは大きなことですね。
グレン・グールドが言っていましたけれど、その楽器の可能性みたいなものの極限を追究していく作曲家と、楽器から離れたところで思考する作曲家の2種類がいる。でも、僕はどちらもやっぱり大事だと思うんです。
とくにこのプログラムに関しては、音楽だけではなくて、その楽器、ヴァイオリン、そしてそのヴァイオリンで行われるいろいろな技術――それも僕はアートだと思うんですよ。決して技巧にフォーカスしたいわけではないけれど、ヴァイオリンという楽器の持っている可能性、それに触発されて書かれた作品、そういうなかで生まれる音楽はすごく面白い。
――ラヴェルにとっての《ツィガーヌ》なんて、まさしくその鮮やかな例ですね。ダラーニという強烈な名手がいたから、この曲ではある意味破目も外せたのだと思いますし。
ほんとうにそう。後にも先にもあんな曲は書いていないし、でもやっぱりラヴェルの音楽に他ならないし、という面白さがありますよね。そういうところが伝わればと思います。
――過去の偉大なヴィルトゥオーゾやその技術に関しては、どんなふうに思われていますか?
サラサーテやイザイ、ダラーニも録音が残っているけれど、やっぱりちょっといまでも驚愕するぐらいの技術を持っている人たちだと思う。どこからそうなったのかはまったくわからないけれど、いまとはぜんぜん違う演奏法をしてたんだろうと感じますね。
――めちゃくちゃ巧いですか? 現代の郷古さんからみても。
イザイの演奏を聴くと、ちょっとびっくりしますよ。ヴァイオリンってこういう楽器だったのか、というふうに思ってしまう。すべてをもっていたような気がしますね。
いまの演奏家をみると、音楽を大事にするのはとてもいいことだけれど、その前に楽器の可能性をみんなでもうちょっと探してもいいんじゃないかって、最近すごく思うんですよ。ハーモニーやスタイルというのもすごく大事なんだけれど、でも、まず美しいビブラート、本当に美しいボウイング、美しいダブルストップの弾きかた、その共鳴のさせかた、美しいハーモニクスやオクターヴ、そういうことにもうちょっとこだわってもいいんじゃないかとも思う。そこからみえてくる音楽性みたいなものがやっぱりあるし。とにかく楽器がちゃんとしゃべっているということが、楽器を演奏するからにはいちばん大事で。
――そうすると、郷古さんにとって、楽器というのはどういうものですか。たんなる自分の感覚の延長というよりは、もっと具体性をもったものでしょう?
そうです。たんなる自分の延長ではないんだけれども、ただ、ヴァイオリンという楽器がもっているものというのは、なにか非常に人間的ではある。むかしからヴァイオリンって、魂というもののたとえに使われていたりしましたしね。非常に幅の広い楽器で、高貴なものも演奏できるけど、本当に吹きさらしのところで演奏されているような楽器でもあるし。
――その魂は、郷古さんの人生よりも長く、古い記憶といろいろな手を知っているわけですよね。大樹に手を触れると遠大な時間が感じられる、というのに近い感覚もありますか?
あります、あります。そして、自分がこの楽器(※)にとってはただの通過点でしかないんだろうなと思う。確実に僕よりも長く残っているだろうし、残っているべきで、その時間の一部を、自分がこの楽器と共有できているのはすごくありがたいことです。特にこういう素晴らしい楽器を手にしていると、本当にそれを強く感じます。ストラディヴァリのなかでも結構若い頃の作品なのですが、14歳から弾いていて、僕はすごくラッキーだと思う。
※郷古廉さんの使用楽器は1682年製アントニオ・ストラディヴァリ(Banat)
――半生よりも長い……。
そう考えるとなにか、体の一部ではないけれど、もう魂の一部とは言っていいかな。
――逆にこのヴァイオリンにとって、郷古さんとの歳月はどんなものだと想像されます?
わからないですけど、たぶんいままでいちばん僕が弾いていると思うんです。こんなに年月が経って、いまもこれだけ弾かれるとは思っていなかったでしょうね(笑)。これほどいろいろな曲を弾かされるとも。この楽器が生まれたとき、いま弾いているような曲はなにもなかったのだし。
――ますます長く、よい旅をお祈りしております。

シリーズ杜の響きvol.52 郷古 廉&ホセ・ガヤルド デュオ・リサイタル
2024年11月17日(日)14:00開演
杜のホールはしもと・ホール
▼チケットのお買い求め▼
◎チケットMove TEL 042-742-9999(10:00~19:00)
◎チケットムーヴ.net http://move-ticket.pia.jp/ticketInformation.do?eventCd=2417430&rlsCd=005